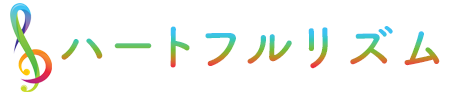童謡「赤とんぼ」の歌詞意味 :切なくて美しい歌詞に隠された意味及び魅力

このフレーズを耳にするだけで、多くの人の心に懐かしい秋の夕暮れが浮かぶのではないでしょうか。
子供の頃、夢中で追いかけた赤とんぼ。切なくて美しいメロディーとともに、日本の原風景を思い起こさせる童謡「赤とんぼ」。
なぜ、この歌はこれほどまでに私たちの心に深く響くのでしょうか?
今回は、誰もが知るこの名曲に隠された、切なくも温かい物語を紐解いていきたいと思います。

歌詞
1、夕焼け小焼けの 赤とんぼ
負われて見たのは いつの日か
2,山の畑の 桑の実を
小籠に摘んだは まぼろしか
3,十五でねえやは 嫁にゆき
お里のたよりも 絶えはてた
4,夕焼け小焼けの 赤とんぼ
とまっているよ 竿の先
作詞:三木露風
作曲:山田耕筰
作詞・作曲について
童謡「赤とんぼ」の作詞、作曲者について簡単に紹介したいと思います。
作詞:三木露風(みき ろふう)
1889年(明治22年)6月23日生~1964年(昭和39年)12月29日没
日本の詩人、童謡作家、随筆家。父弟に映画カメラマンの碧川道夫がいます。また国木田独歩の曽祖母が三木家出身である。
近代日本を代表する詩人、作詞家とし北原白秋と並んで「白露時代」を築いた。若き日は日本における象徴派詩人でもあった。
明治22年6月23日現兵庫県たつの市に生まれ、に父・三木節次郎、母・かたの長男として生まれた。5歳の時に両親が離婚し、祖父の元に引き取られて育てられた。早熟の天才であり、小中学生時代から詩、短歌、俳句を新聞や雑誌に寄稿していた。後、早稲田大学、慶応義塾大学で学びました。
作曲 : 山田耕筰(やまだ こうさく)
1886年(明治19年)6月9日生~1965年(昭和40年)12月29日没
日本の作曲家、指揮者。福島藩士で医者、キリスト教伝道師の山田建造の子として生まれました。
10歳の時に実父を亡くした。実父の遺言で、巣鴨宮下にあった自営館(後の日本基督教団巣鴨教会)に入館し、13歳まで施設で苦学する。姉のガントレット恒を頼り岡山の養忠学校に入学し、あねの夫のエドワード・ガントレット(イギリス出身の英語教師、音楽家、英国パイプオルガン技師)に西洋音楽の手ほどきを受けました。後1908年に東京音楽学校(後の東京芸術大学)声楽科を卒業しました。
「赤とんぼ」の歌詞を紐解く
老若男女を問わず、最も人気が高い童謡といえばやっぱ「赤とんぼ」だと思います。何となくこの光景は、幼い時に体験している、、、、。と共感するのではないでしょうか?
しかし、この童謡は一般に知られるまで、相当時間を要したみたいです。
童謡「赤とんぼ」が人気が出るまでのエピソー誌
この詞は、天才肌の三木露風が、わずか13歳で雑誌「小国民」に詩や散文を発表していました。俳句として『赤とんぼ とまっているよ 竿の先』と発表していました。
この句を原形に「赤とんぼ」が童謡雑誌の『樫の実』に発表されたのが、大正10年(1921年)8月露風が32歳のときでした。
しかし、山田耕筰が曲をつけたのは、6年後の昭和2年(1927年)でした。更に4年後にレコードにはなったものの、全く人気もなく世に知られることもなかったようです。
後、昭和30年(1955年)にこの曲が生まれて30年近い年月が流れて、映画のワンシーンでこの曲が使われたのでした。この映画は松竹映画『ここに泉あり』(今井正監督、小林桂樹、岸恵子主演)であります。映画を見た客からすぐさま反応があっという間に、一躍有名になったそうです。
「赤とんぼ」の歌詞を紐解く
ざっと歌詞を要約すると以下のようになります。
- 1番: 「夕焼け小焼けの赤とんぼ」から始まる情景描写。日本の秋の夕暮れを鮮やかに描き出します。
- 2番: 「山の畑の桑の実を」で、主人公(少年・少女)の過去の思い出が語られます。「赤とんぼ」が、かつて自分をおんぶしてくれた姉(ねえや)を連想させる存在であることが示されます。
- 3番: 「十五でねえやは嫁に行き」で、姉との別れが描かれます。この部分で、歌全体の切ない感情が最高潮に達します。
- 4番: 「小 籠に摘んだは幻か」で、過去の思い出がもう戻らない、遠い記憶であることを強調します。
2番の歌詞の♪おわれて みたのは いつのひか、、、♪とあります。これを ”追われて” と勘違いしている人がいます。”赤とんぼに追われている” やまたは”赤とんぼを網で捕まえようと追っているのか ”と思いっている人もいます。これは勘違いです。
”追われて”でなく”負われている”なのです。誰かの背中に追われているのです。
また更に〝だれに負われているのか ”と論議されました。ほとんどの人は母親かと思いましたが、この詩の中に母親は全く登場しません。だから十五で嫁に行った姐やである、という意見が浮上しました。姐やとは当時女中さんと呼ばれた子守り奉公の女の子のことなのです。母親はというと、露風が六歳を迎える年に父親と離縁して、小さい時分からいなかったと想像され、追われる年齢はおそらく6歳より下であろうと思われます。
後に三木露風自身で書いた内容に「この童謡赤とんぼは、懐かしい心持から書いた。姐やとあるのは、私の子守娘が、私を背負うて広場で遊んでいた。その時、私が背の上で見たのが、赤とんぼである。」
と書いています。おそらく露風の家は裕福ではあったが、母親が離婚して実家に帰ってしまいました。すぐに父親が再婚し弟も産まれています。母親を慕う寂しい気持ちもあるのだと思われます。この心の内が、この童謡を作り、日本の名曲に育っていったのでした。
引用:「案外、知らずに歌ってた 童謡の謎 」 合田道人 著よりhttps://amzn.to/476z1LP
なぜ「赤とんぼ」はこれほどまでに心に響くのか?
- 懐かしさの象徴: 多くの日本人にとって「赤とんぼ」は、子供の頃の思い出や故郷の風景と結びついています。
- 切ない「別れ」の歌: 単なる秋の歌ではなく、大切な人との別れ、そして二度と戻らない過去への追想がテーマになっています。
- 美しい情景描写: 三木露風による詩は、日本の里山の風景や、夕暮れの光、風の匂いまで感じさせるほど繊細で美しい言葉で紡がれています。
声楽家 鮫島有美子さんの「赤とんぼ」も素敵でしたので、掲載しました。
まとめ:「赤とんぼ」は現代にも生きている
「赤とんぼ」は、単なる童謡ではなく、私たちの心の中にある「故郷」や「大切な人との思い出」を呼び覚ます、特別な歌です。
秋の夕暮れ時にこの歌を聴くと、なぜか涙が出そうになるのは、歌詞に込められた普遍的な「切なさ」が、私たちの心に深く響くからかもしれません。
Amazon ふるさと納税👇