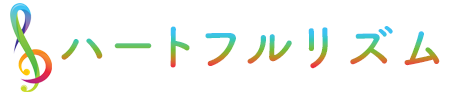オーボエとは:なぜ世界一難しい木管楽器といわれているか(構造と理由)

他の楽器に比べて、その存在は少し控えめかもしれない。しかし、オーケストラの中で一度その音色を耳にすれば、決して忘れることはない。甘く、そしてどこか憂いを帯びたその響きは、人の心の奥深くにそっと触れてきます。
この楽器は、演奏者の息遣いそのものが音になる。わずかな空気の加減、唇の震え、指先の繊細な動き。そのすべてが合わさって、たった一つの、しかし唯一無二のメロディを紡ぎ出します。それはまるで、奏者の心の声を聞いているかのようです。
オーボエってどんな楽器?

吹奏楽器の一種であり、※ダブルリードで発音する円錐管の楽器である。原義はフランス語ののhautbois(高い木)で、「高音(または大音量)の木管楽器」であるとされます。
※ダブルリードは、乾燥させた葦を削ったものを二枚重ね合わせて作られ、これを楽器の吹口に取り付けて吹くことで振動させる。
吹奏楽器の一種であり、※ダブルリードで発音する円錐管の楽器である。原義はフランス語ののhautbois(高い木)で、「高音(または大音量)の木管楽器」であるとされます
※ダブルリードは、乾燥させた葦を削ったものを二枚重ね合わせて作られ、これを楽器の吹口に取り付けて吹くことで振動させる。
主な特徴
- ダブルリード楽器
- オーボエの音を出すために最も重要な部分が「リード」です。2枚のリードの間に息を吹き込むことで、リードが振動して音が鳴ります。このリードは非常に繊細で、奏者自身が削って調整することが一般的です。
- オーケストラの音合わせ
- オーケストラでは、開演前のチューニング(音合わせ)の際に、オーボエが最初に「A(ラ)」の音を出します。これは、オーボエの音程が比較的安定していて、音色がよく通るためです。
- 「世界一難しい木管楽器」
- ギネスブックにも「世界一難しい木管楽器」として記載されています。繊細なリードの調整や、少ない息で音をコントロールする技術など、習得には高い技術が求められます。
- 多様な表現力:
- オーボエは、繊細で優美な音から、力強く明るい音まで幅広い音色を出すことができます。この表現力の豊かさから、多くの作曲家がソロパートを書いています。
構造と種類
- 構造:
- オーボエは、主にグラナディラなどの木材で作られており、上管・下管・ベルの3つの部分で構成されています。たくさんのキー(鍵)がついており、これを操作して音程を変えます。
- 種類:
- オーボエには、いくつかの種類があります。
- オーボエ・ダモーレ: オーボエよりも少し低い音域を担当する楽器。
- コーラングレ(イングリッシュホルン): オーボエよりも完全5度低い音域の楽器で、特に深い哀愁を帯びた音色が特徴的です。ドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」の第2楽章のソロが有名です。
- バスオーボエ: オーボエより1オクターブ低い音域を持つ楽器で、使用されることは比較的稀です。
- オーボエには、いくつかの種類があります。
- システム:
- キーのシステムには主に「フルオートマティック」と「セミオートマティック」があり、セミオートマティックが広く使われています。
- また、オーボエのタイプには「フランス式(コンセルヴァトワール式)」と、ウィーンの奏者が主に使用する「ドイツ式(ウィンナーオーボエ)」があります。
歴史
オーボエの祖先は、中世ヨーロッパの「ショーム」というダブルリードの楽器に遡ると言われています。17世紀中頃にフランスで改良され、現在のオーボエに近い形が誕生しました。その後、キーの改良が進み、19世紀にはフランスの楽器製作者によって現在のスタンダードなシステムが確立されました。バッハやモーツァルトなどの古典派から、チャイコフスキー、ラヴェルといった近代の作曲家まで、多くの作品でその美しい音色が使われています。
コーラングレ(イングリッシュホルン)ってホルンなのになぜオーボエ?
イングリッシュ・ホルンは、コーラングレ(Cor Anglais)とも呼ばれ、オーボエよりも5度低い移調楽器。 つまり、楽譜上のCの音は、5度低いFの音となって発音される。 オーボエの同族楽器だが、音域が低い分、管が長く、また、ベル(あさがお)が、球状にふくらんでいる点が異なっている。 17世紀頃、ショームから生まれたといわれ、オーボエ・ダ・カッチャ(狩りのオーボエ)と呼ばれたこともあった。
オーボエが難しい理由は、主に以下の3点に集約されます。まず、リードの扱いや息のコントロールが難しく、音を出すこと自体が容易ではありません。次に、音程を安定させるのが難しく、特にpp(ピアニッシモ)などの小さな音を出すのが困難です。最後に、運指が複雑で、半音や変化音を出すのが難しいとされています。
オーボエはなぜ難しいのか
- リードの扱いの難しさ:オーボエはダブルリード楽器であり、2枚のリードを振動させて音を出すため、リードの調整や口の当て方など、リードの扱いに熟練が必要です。
- 音を出すことの難しさ:リードの調整や口の形、息の入れ方など、音を出すための条件が複雑で、初心者にはなかなか音が出せない、あるいは音が出てもコントロールが難しいという状況になりがちです。
- 音程の安定の難しさ:オーボエは、わずかな息の量や口の形の変化で音程が変わりやすく、音程を安定させるのが難しい楽器です。特に、ppなどの小さな音を出すのが難しく、音程が不安定になりやすい傾向があります。
- :オーボエの運指は、他の木管楽器に比べて複雑で、半音や変化音を出すためのキー操作が難解です。また、指の動きも他の楽器に比べて複雑で、習得に時間がかかります。
これらの理由から、オーボエは「世界一難しい木管楽器」とも言われており、ギネスブックにもそのように認定されているほどです。しかし、その分、演奏できた時の喜びも大きく、挑戦しがいのある楽器と言えるでしょう。
楽器を保管することの難しさ
オーボエは、適切な温度や湿度のなかで保管しなければならない、非常にデリケートな楽器です。多湿はもちろんだめですが、楽器が乾き過ぎても管体にヒビが入ったりします。また急な温度変化のなかに置いておくと、キーが動作しなくなることもあります。
オーボエを保管する最適な場所は、人が暮らしている生活空間です。こうした場所は風通しがよく、季節によって空調管理もされているからです。オーボエを車のなかに放置したり、湿度や温度のこもりやすいクローゼットのなかに長期間置いたりすることは避けましょう。演奏後には、クリーニングスワブやクリーニングペーパーを使って、管体内やタンポに残っている水分を完全にふき取っておくことも必要です。またリードは乾燥すると割れてしまいます。高温多湿の真夏以外は、密封できるビニール袋などにリードを入れて保管するようにしましょう。
オーボエ演奏の動画
オーボエの演奏を聴いていると、なぜだか温かさに涙が出ます。この世に生まれてきた人達に、少しでも幸せに暮らしてほしい、平和な世界を望む人が増えますようにと祈る気持ちになります。
あまりに戦争など恐ろしさを見過ぎて、心が痛みます。
オーボエ:広田智之(東京都交響楽団首席奏者・ソリスト) ピアノ・編曲:美野春樹
まとめ:オーボエの音色に魅せられて
オーボエの音色は、まるで森の奥から聴こえてくるような、どこか懐かしく、そして心を揺さぶる特別な響きです。
これからオーボエを習う方は、最初は戸惑うことも、うまくいかずに投げ出したくなることもあるかもしれません。でも、オーボエを続けることは、自分自身と向き合う旅でもあります。少しずつ音が出せるようになり、思い通りの音色を奏でられるようになったとき、そこには何物にも代えがたい喜びが待っていると思います。
オーボエは、あなたの人生に豊かな彩りを添えてくれます。音楽を愛する仲間との出会い、コンサートで聴衆と感動を分かち合う瞬間、そして何より、あなた自身の心の中に、かけがえのない宝物が生まれるでしょう。